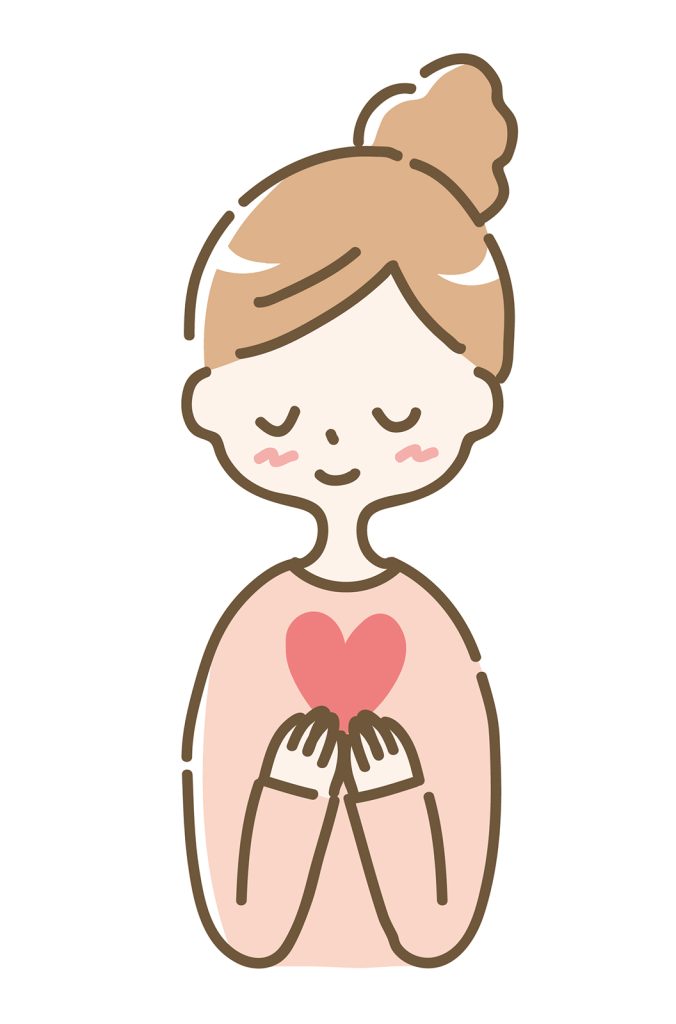期間限定、甘い恋
夏の終わり、街はまだ暑さを引きずっていたけれど、どこか寂しさが漂っていた。季節が変わるその瞬間、何かが終わり、また新しい何かが始まる。その予感が胸に広がっていた。
あの日、君と出会ったのは偶然だった。僕は友達に誘われて参加した夏祭りで、君と初めて顔を合わせた。浴衣を着た君は、まるで絵に描いたような美しさで、すぐに目を奪われた。君の瞳の奥に、どこか儚いものを感じて、心がざわついた。
「こんにちは」と声をかけたのは僕の方だった。君は少し驚いた顔をして、それからにっこり笑った。あの笑顔が、僕にとってはこの上ない贈り物のように思えた。
「こんにちは。こんなところで会うなんて珍しいね。」
君のその一言が、僕の胸を打った。何も特別なことは言っていないのに、君の言葉はどうしてこんなに心に響くんだろう。僕たちはそのまま、一緒に祭りの屋台を回ることにした。君が喜んでくれる顔が見たくて、いろんなものを一緒に買ったり食べたりした。
でも、夏祭りが終わると、君との距離が少しずつ離れていった。君は東京に住んでいて、僕はこの町で暮らしていたから、実は会うのは難しかった。それでも、君からたまに送られてくるメッセージに、どこか安心していた。お互いに「また会おうね」と言いながらも、その言葉が少し寂しく感じられた。
その後、君が次に来ることを知らせてくれたのは、秋の初めだった。僕はまた、君に会えることを心待ちにしていた。約束の場所で待っていると、君がゆっくりと歩いてきた。今日はいつもと違って、少し大人びた装いをしていた。髪を軽くまとめ、少しメイクもしていた君が、何だかとても素敵で、僕は胸が高鳴った。
「久しぶり。」君は僕を見つけると、少し照れたように言った。
「久しぶりだね。元気だった?」
僕は、君が本当に元気だったかどうかなんて分からない。でも、君が笑っているなら、それでいいと思った。僕たちはまた、あの日のように街を歩いた。秋風が心地よく、紅葉が色づき始めた公園で、僕たちは並んで歩いた。
その日、君が言ったことが忘れられない。「実はね、東京に戻る前に、もう少しだけ君と一緒にいたいんだ。」その言葉に、僕は胸が締め付けられるような気持ちになった。君はすぐに続けた。「でも、それはただの夏の思い出として、心の中にしまっておくつもりだったの。だから、そんなことを言うのは、変だよね。」
僕は少し考えてから答えた。「変なんかじゃないよ。」心の中では、君の言葉が痛くて、でも嬉しくて、なんとも言えない感情が込み上げてきた。君と過ごす時間は、もうすぐ終わりが来ることを分かっている。でも、それでもいい。君との「期間限定の甘い恋」を、僕は大切にしたかった。
それから、僕たちは一緒に過ごす時間を一瞬一瞬、精一杯楽しんだ。君と一緒に見る秋の空、夕暮れ時に並んで歩く道、手をつないで笑い合うひととき。どれもが甘く、そして切なかった。君はもうすぐ東京に帰るという事実を知りながらも、僕はその日々をただ甘美な夢のように感じていた。
そして、最後の日が来た。君は早朝に出発する予定だった。僕は、君を駅まで送り届けることにした。改札の前で、君は少し寂しそうな顔をしていた。僕はその顔を見るたびに、心が痛んだ。
「ありがとう、いろいろなことを教えてくれて。楽しかったよ。」君が言ったその言葉に、僕は答えられなかった。言葉にするのが怖かった。君が笑顔で去っていくその後ろ姿を見送るのが、僕にとっては一番辛かった。
「また会えるよね?」君は振り返り、少し不安そうに言った。
「うん、また。絶対に。」その言葉だけは、どうしても伝えたかった。僕たちの恋がどれほど短くても、どれほど切なくても、君と過ごした時間は、確かに僕の中に残る宝物だ。
君はそのまま、駅のホームに消えていった。僕は、君が見えなくなるまで、ずっとその場所で立ち尽くしていた。
「期間限定、甘い恋」だったけれど、その思い出は永遠に色あせることなく、僕の中で輝き続けるだろう。君と過ごした日々は、今でも僕の心の中であたたかく、甘い思い出として生きている。